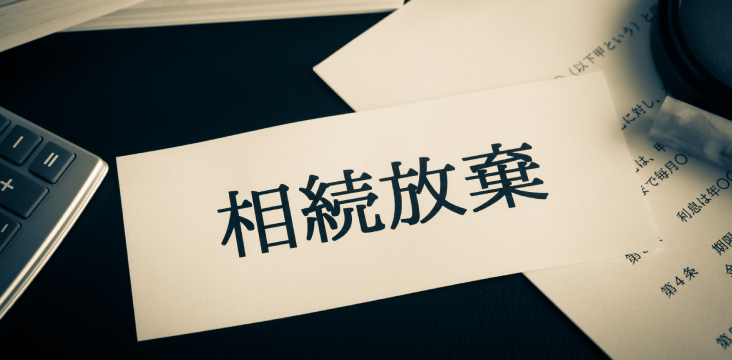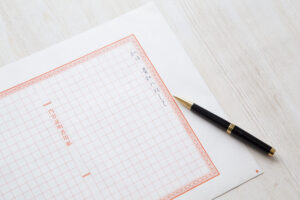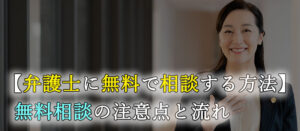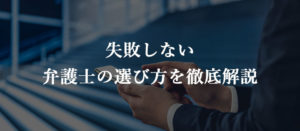トラブルが起きてしまい弁護士に相談したい。けれど、「どれくらい費用がかかるのかわからない」「高いって聞くけど本当?」「自分の経済力で払えるのかな」など、不安に感じている方は多いのではないでしょうか。
この記事ではどういったケースで弁護士費用はいくら必要なのか、弁護士費用を支払えない場合どうすればいいのかを解説していきます。
法律トラブルが発生した際、状況によっては高額な弁護士費用が必要になることもありますが、事前にベンナビ弁護士保険に加入しておけば弁護士費用の負担を軽減できます。
- 保険料は1日たった約96円※2
- 初回60分相談料が無料の弁護士をご紹介
- 追加保険料0円で家族も補償に
※1 2021年6月時点
※2 年間の保険料35,400円を365日で割った金額

弁護士費用の内訳は?一覧表で解説
|
費用項目 |
費用相場 |
支払うタイミング |
|
相談料 |
30分あたり5,000円 |
相談時 |
|
着手金 |
経済的利益の2~8%+α ※ただし、最低額は10万円とされることが多いです。 |
依頼時 |
|
報酬金(成功報酬) |
経済的利益の4~16%+α |
事件等の処理が終了した時 |
|
手数料 |
案件次第 |
依頼時 |
|
実費や日当 |
案件次第 |
ケースバイケース |
弁護士費用は主に、相談料・着手金・報酬金・手数料・実費や日当の5つに分けられます。
過去には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によって、弁護士費用が定められていましたが、現在は各法律事務所が自由に設定できるようになっています。
そのため、弁護士費用には厳密に「相場」というものは存在しないのが実情です。とはいえ、過去の基準を元に費用を決めている法律事務所も多いので、目安とすることは可能です。
ここからは、依頼内容ごとに(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考にしながら、弁護士費用を解説していきます。
なお、実際に法律事務所に相談や依頼をする場合には、その事務所が設定している弁護士費用を確認するようにしましょう。
相談料|初回は相談料無料の法律事務所が多い
相談料とは弁護士に相談した際にかかる費用のことです。金額は30分あたり5,000円が相場とされています。
現在は初回の相談を無料にしている事務所も多いので、「費用を極力抑えたい」「まずは話を聞いてほしい」という方はそういった法律事務所を利用するとよいでしょう。
【関連記事】弁護士に無料法律相談ができるのはどこ?電話相談・24時間相談受付の窓口を紹介
着手金|経済的利益の2~8%+αが目安
着手金とは、弁護士に事件を依頼した際に最初に支払う費用のことです。
弁護士が仕事を引き受けて活動を開始するための契約金のようなもので、事件処理の結果に関係なく着手時に支払う必要があります。
金額は法律事務所によってさまざまですが、民事事件の場合は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に準じて、以下の計算式で算出している事務所が多いようです。
|
経済的利益の額 |
着手金 |
|
300万円以下 |
経済的利益の8% ※ただし、最低額は10万円とされることが多いです。 |
|
300万円を超え、3,000万円以下 |
経済的利益の5%+9万円 |
|
3,000万円を超え、3億円以下 |
経済的利益の3%+69万円 |
|
3億円を超える |
経済的利益の2%+369万円 |
【参考】(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
なお、経済的利益とは、事件の対象となっている利益や事件処理によって確保した利益のことで、相手に請求する金額などがこれに該当します。
依頼する際はその法律事務所がどのような料金設定にしているのかを確認する必要があります。
報酬金(成功報酬)|経済的利益の4~16%+αが目安
成功報酬とは、事件処理の成果に応じて支払われる費用のことです。着手金と同じく経済的利益を基に算出されます。
法律事務所によって設定はまちまちですが、民事事件の場合は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に準じて、経済的利益の4~16%+αと設定している法律事務所が多いようです。
手数料|1回程度で終了する手続にかかる費用
手数料とは、契約書・遺言書の作成や登記など、1回程度で終了する手続を依頼した場合に支払う費用です。
実費・日当|実際に発生する費用・時間的拘束の対価
実費とは、裁判を起こす際の裁判所に納付する印紙代や切手代、記録の謄写費用など、事件処理のために実際に発生する費用です。
保証金・不動産鑑定料のほか、弁護士の出張が必要な場合には交通費や宿泊費等も支払う必要があります。
日当とは、弁護士が事務所から移動することによって、その事件の処理のために時間的に拘束される際に支払われる費用です。たとえば、裁判所に出廷するごとに支払われる出廷日当などがあります。
トラブル別弁護士費用の相場と計算方法
ここから先は事案ごとにどれくらい費用がかかるのかを紹介します。なお、料金設定は法律事務所によって異なるので、あくまでも目安として理解しておきましょう。
離婚トラブルの解決にかかる弁護士費用
離婚トラブルを依頼した場合、相談料が5,000~1万円、着手金は20万~50万円程度が一般的です。また、内容によっては以下の費用・報酬が追加で発生します。
|
依頼内容 |
費用 |
|
慰謝料請求 |
経済的利益に基づいて算定された着手金・報酬金 |
|
財産分与 |
経済的利益に基づいて算定された着手金・報酬金 |
|
親権争い |
10万~50万円 |
|
養育費 |
経済的利益に基づいて算定された着手金・報酬金 ※将来の養育費についての経済的利益は、数年分の養育費の金額とされることが多いようです。 |
遺産相続トラブルの解決にかかる弁護士費用
着手金は数十万円となることが多いようです。ただし、事案の難易度や想定される経済的利益の大きさによっては数百万円を超えることもあるので、依頼先の法律事務所に確認するようにしましょう。
トラブルの内容に応じて発生する弁護士費用の相場は次のとおりです。
遺産分割の代理の場合
遺産分割の代理を依頼した場合は、経済的利益の大きさによって着手金や報酬金が変動します。対象となる相続分の時価相当額を経済的利益とすることが多いようです。
報酬金の額は法律事務所によってさまざまですが、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に準じて以下のように計算されることが多いでしょう。
|
経済的利益の額 |
報酬金 |
|
300万円以下 |
経済的利益の16% |
|
300万円を超え、3,000万円以下 |
経済的利益の10%+18万円 |
|
3,000万円を超え、3億円以下 |
経済的利益の6%+138万円 |
|
3億円を超える |
経済的利益の4%+738万円 |
仮に、依頼によって得られた経済的利益が200万円の場合、32万円が報酬として算定されます。
遺言書の作成も、遺産の総額や内容の複雑さによって変動するため一定の相場はありません。
(旧)日本弁護士連合会の報酬等基準によると、一般的な遺言内容がメインとなる「定型」の遺言書作成の場合は、10万~20万円の範囲内と定められているため、参考にするとよいでしょう。
また、非定型の場合の遺言書作成費用は、経済的利益に応じた段階的な報酬を参考にしてください。
|
経済的利益の額 |
手数料 |
|
300万円以下 |
20万円 |
|
300万円を超え、3,000万円以下 |
経済的利益の1%+17万円 |
|
3,000万円を超え、3億円以下 |
経済的利益の0.3%+38万円 |
|
3億円を超える |
経済的利益の0.1%+98万円 |
また、遺言書を公正証書にする場合は、別途3万円程度の手数料が加算されます。
遺言執行の場合
遺言の執行にかかる弁護士費用も経済的利益に応じて大きく変動します。ただし、最低でも30万円はかかるものと思っておくとよいでしょう。
|
経済的利益の額 |
手数料 |
|
300万円以下 |
30万円 |
|
300万円を超え、3,000万円以下 |
経済的利益の2%+24万円 |
|
3,000万円を超え、3億円以下 |
経済的利益の1%+54万円 |
|
3億円を超える |
経済的利益の0.5%+204万円 |
相続放棄の場合
相続放棄は裁判所への手続が必要となるだけでとくに誰かと争うわけではないので、手数料だけで済むケースが多いでしょう。手数料の目安は10万円程度です。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の場合
遺留分を侵害された場合に、相手に遺留分侵害額請求の意思表示をすることの代理だけであれば3万~5万円程度の手数料がかかるだけの場合が多いでしょう。
一方で、遺留分に関する法的手続をとる場合などは、経済的利益によって弁護士費用の額が変動します。
|
経済的利益の額 |
報酬金 |
|
300万円以下 |
経済的利益の16% |
|
300万円を超え、3,000万円以下 |
経済的利益の10%+18万円 |
|
3,000万円を超え、3億円以下 |
経済的利益の6%+138万円 |
|
3億円を超える |
経済的利益の4%+738万円 |
交通事故トラブルの場合
交通事故の被害に遭った、交通事故を起こしてしまったといったトラブルで弁護士に解決を依頼した場合は、着手金として経済的利益の2~8%+α(ただし、最低額は10万円)、報酬金として経済的利益の4~16%+αの弁護士費用が目安となります。
刑事事件の場合
刑事事件の容疑者(被疑者)とされてしまった場合の刑事弁護費用は、着手金・報酬金ともに20~50万円程度がかかるため、トータルで40万~100万円程度が目安です。
接見回数が多い場合や、無罪判決の獲得を目指す場合など難易度が高い事件ではさらに高額になることもあります。
労働トラブル(労働者側)の場合
以下のような労働に関するトラブルの解決を依頼した場合の着手金は、経済的利益の2~8%+α(ただし、最低額は10万円)が目安です。報酬金は獲得した経済的利益の4~16%+αが目安です。
- 残業代請求
- 不当解雇
- 労働災害
- パワハラ・セクハラ
なお、経済的利益を金銭に換算するのが難しい場合には、「800万円の経済的利益とみなす」などとされることもあります。
債権回収の場合
債権回収を依頼した場合は、着手金として経済的利益の2~8%+α(ただし、最低額は10万円)、報酬金として経済的利益の4~16%+αの弁護士費用が目安となります。
債務整理
借金の返済を軽くしたい、借金をなくしたいといった債務整理に関する相談の場合、弁護士費用の目安は次のとおりです。
|
依頼内容 |
費用 |
|
任意整理 |
債権者1社あたり3万~10万円 |
|
個人再生 |
50万~60万円 |
|
自己破産 |
20万~50万円 |
インターネット上のトラブルの場合
以下のようなインターネット上における誹謗中傷などのトラブルでは、削除依頼・加害者の特定・損害賠償の請求についてそれぞれ弁護士費用がかかります。
- 誹謗中傷・風評被害
- リベンジポルノ
- 著作権・商標権侵害
- 自身の犯罪歴の削除依頼
「投稿を削除したい」と依頼した場合は、裁判手続によらない方法だと5万円~、裁判手続による方法だと20万円~程度が着手金の目安となります。
加害者を特定したい場合は、二段階の発信者情報開示請求が必要となることがあり、それぞれの手続について、20万円~程度が着手金の目安となります。
加害者を特定した後、加害者に対して損害賠償を請求する場合は、経済的利益の2~8%+α程度の着手金が目安となります。
さらに、獲得した賠償金の4~16%+α程度の報酬金が目安となります。
企業法務
企業法務のサポートを弁護士に依頼する場合は、依頼内容によって費用が異なります。
顧問弁護士の場合
顧問弁護士契約は月額3~30万円程度が目安です。会社の規模や対応する業務内容などによって段階的なプランを用意している事務所もあるため、都合にあわせてプランを選択するとよいでしょう。
破産・民事再生の場合
破産・民事再生の依頼は、資本金、資産・負債額、関係人の数などによって着手金・報酬金が変動します。
事業者の自己破産については、着手金は50万円~、報酬金は経済的利益の4~16%+αが目安です。事業者の民事再生については、着手金は100万円~、報酬金は経済的利益の4~16%+αが目安となります。
IPOサポートの場合
上場のサポートを顧問弁護士に依頼する場合、顧問料として月額3~30万円程度が必要となるほか、追加の弁護士費用が必要となることがあるでしょう。
事業承継の場合
事業継承のサポートを依頼した場合の弁護士費用は法律事務所によってさまざまです。着手金・報酬金の方式のほか、1時間あたりいくらといったタイムチャージの方式をとる場合もあるでしょう。
M&Aの場合
M&Aのサポートを依頼した場合の弁護士費用についても法律事務所によってさまざまです。着手金・報酬金の方式のほか、1時間あたりいくらといったタイムチャージの方式をとる場合もあるでしょう。
契約書の作成・リーガルチェックの場合
各種の契約書作成・リーガルチェックを顧問弁護士に依頼する場合、顧問料として月額3~30万円程度が必要となります。
その他民事事件の場合
これまであげたトラブル以外にも、弁護士に頼るケースは数多くあります。
不動産トラブルの場合
着手金として経済的利益の2~8%+α(ただし、最低額は10万円)、報酬金として経済的利益の4~16%+αの弁護士費用が目安です。この場合、不動産の時価相当額が経済的利益とされることがあります。
医療過誤の場合
事案の難易度によって変動しますが、着手金として経済的利益の2~8%+α(ただし、最低額は10万円)、報酬金として経済的利益の4~16%+αの弁護士費用が目安です。
消費者トラブルの場合
トラブルの内容によって変動しますが、着手金として経済的利益の2~8%+α(ただし、最低額は10万円)、報酬金として経済的利益の4~16%+αの弁護士費用が目安です。
弁護士費用は誰が払う?相手に請求できる?
原則として、弁護士費用は裁判の勝った・負けたに関係なく自分で支払う必要があります。
ただし、相手の不法行為を理由に損害賠償を請求する場合などでは、例外的に弁護士費用の請求が可能です。たとえば、暴力によってケガをした場合、弁護士費用も損害賠償の金額に加算されることがあります。
ただし、不法行為があった場合に必ず相手に請求できるとは限りませんし、実際にかかった弁護士費用の全額が認められるわけでもありません。弁護士費用は自分で負担するものとして認識しておいたほうがよいでしょう。
法律トラブルが発生した際、状況によっては高額な弁護士費用が必要になることもありますが、事前にベンナビ弁護士保険に加入しておけば弁護士費用の負担を軽減できます。
- 保険料は1日たった約96円※2
- 初回60分相談料が無料の弁護士をご紹介
- 追加保険料0円で家族も補償に
※1 2021年6月時点
※2 年間の保険料35,400円を365日で割った金額
弁護士費用が高すぎる!払えない場合どうすればいい?
このように弁護士費用は高額となることがあり、自分の経済力だけでは賄えないケースもあるでしょう。ここでは弁護士費用が払えない場合に備えて知っておいてほしい4つのポイントについて解説をします。
法テラスの立替制度を利用する
法テラス(日本司法支援センター)がおこなっている弁護士費用の立替制度の利用を考えましょう。法テラスとは、法的なトラブルを解決するための案内が受けられる公的な機関のことです。
収入・資産や勝訴の見込みなど一定の条件を満たせば、法テラスに弁護士費用を立て替えてもらえます。利用者は、事件終了後3年以内を目安に、法テラスに月々分割で立替金を返済することになります。
経済的に弁護士に依頼することが難しいと考えている方は以下のリンクから詳しい利用条件を調べてみてください。
初回の相談料が無料の法律事務所に相談する
相談料は30分につき5,000円が目安です。そのため、少しでも費用を抑えたいなら初回の相談料が無料の法律事務所を利用するのがよいでしょう。
話したい内容をその場でうまくまとめられず、きちんと相談できなかったということも想定されます。そうならないように、事前に相談したい内容を整理しておくとよいでしょう。
【関連記事】弁護士に無料法律相談ができるのはどこ?電話相談・24時間相談受付の窓口を紹介
後払いや分割払いができないか相談する
弁護士費用を後払いや分割払いにできる法律事務所を選ぶというのもおすすめです。
現在は支払方法について柔軟に対応してくれる法律事務所も増えてきているので、依頼する前にこういった支払方法ができるか確認しておくとよいでしょう。
トラブルが起きる前なら、弁護士保険で備えておくのも手
トラブルが起きる前なら弁護士保険に加入するのがおすすめです。弁護士保険とは、弁護士費用をカバーするための保険です。
隣人とのトラブルや離婚問題、子どものいじめといった幅広いケースで利用でき、月々の保険料も3,000円程度と少額で済みます。
加入直後や加入前に既に発生しているトラブルの場合は保険金が出ませんが、「将来相続で揉めそう」「子どもが成人したら離婚したい」といった方は事前に加入しておくとよいでしょう。
弁護士費用に関するよくある質問
ここからは、弁護士費用に関するよくある質問を紹介します。
弁護士費用で経済的利益とありますが、どういう意味でしょうか。
経済的利益とは、請求したりされたりする金額、請求によって獲得できた金額、不動産の所有権の時価相当額、獲得した遺産額などを指します。
また、交渉によって借金や慰謝料などが減額された場合も、減額分が経済的利益となります。
こちらの事情で裁判を取り下げた場合の弁護士費用はどうなりますか
着手金は返還されず、そこまでにかかった実費を支払う必要がある場合が多いでしょう。
法律事務所によって取扱いが異なるため、詳しくは依頼先の法律事務所に問い合わせましょう。
訴状や答弁書などの作成や書類の郵送料は着手金に含まれますか?それとも別料金ですか?
訴状や答弁書などの作成については着手金に含まれるのが一般的です。一方、書類の郵送料や裁判所に支払う印紙代は実費として支払う必要があります。
まとめ|もしもに備えるなら弁護士保険への加入を検討しよう
このように弁護士費用は高額になる場合があります。急にお金が必要になっても自分の経済力だけではカバーできない、という方も多いのではないでしょうか。さらにトラブルが起きた直後は精神的にも参ってしまいがちです。
そのため、いつ・何が起きてもよいように弁護士保険に加入しておくのがおすすめです。毎月3,000円程度の保険料で高額な弁護士費用をカバーできるので、経済的にも精神的にも安心感を得られるでしょう。
法律トラブルが発生した際、状況によっては高額な弁護士費用が必要になることもありますが、事前にベンナビ弁護士保険に加入しておけば弁護士費用の負担を軽減できます。
- 保険料は1日たった約96円※2
- 初回60分相談料が無料の弁護士をご紹介
- 追加保険料0円で家族も補償に
※1 2021年6月時点
※2 年間の保険料35,400円を365日で割った金額