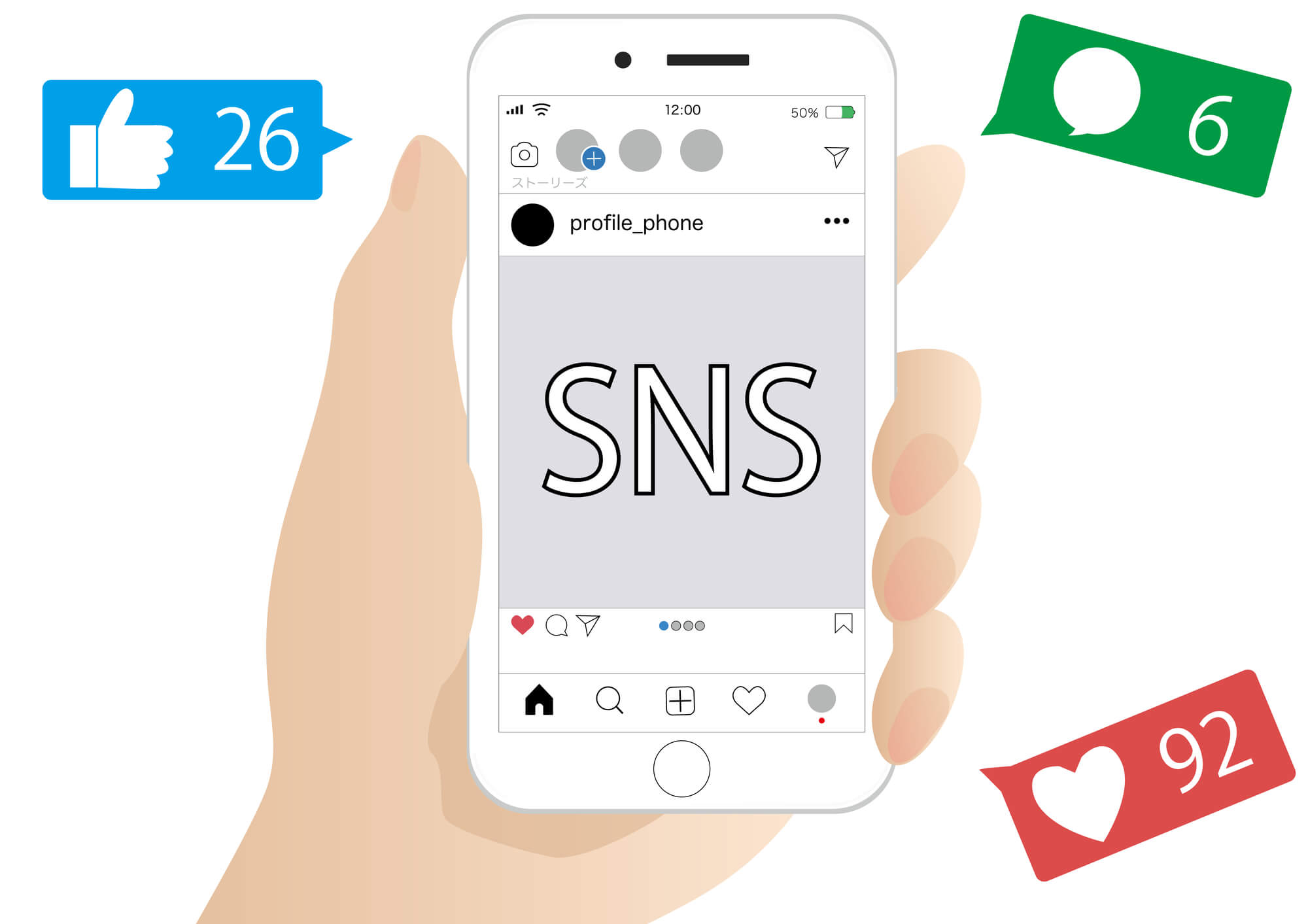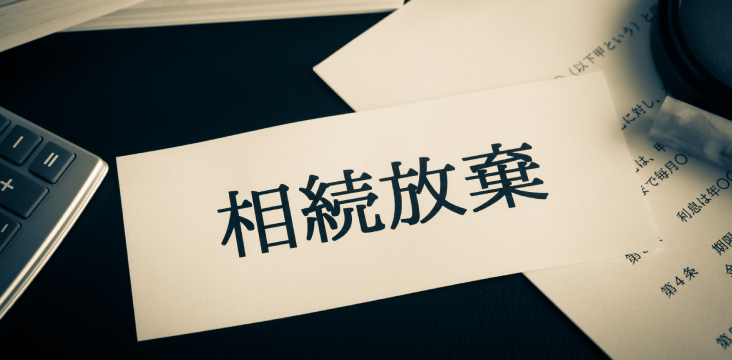「ネットでつぶやいただけなのに名誉毀損?」「知らないところで誹謗中傷されていた!」、現代はそんなリスクが増える一方の現代。
名誉毀損のトラブルに巻き込まれないためにも、その内容についてしっかりと理解し、いざというときには弁護士に依頼して解決してもらうのが望ましいでしょう。
そのための準備として、弁護士費用保険への加入も併せて考えておきましょう。
ネット上での名誉毀損被害は誰にでも起こりうるリスクです。そんなリスクに備える保険
近年SNSや掲示板サイトの利用者が増えるにつれて、トラブルに巻き込まれるケースが増えています。
ネット上での誹謗中傷や名誉毀損などの被害で弁護士に依頼した場合、弁護士費用は100万円前後かかることがあります。
しかし、名誉毀損の被害による慰謝料相場は個人の場合10~50万円程度と弁護士費用のほうが高くなるため、泣き寝入りしてしまう可能性がありますが、ベンナビなら↓↓↓
- ✔保険料は1日たった約96円※
- ✔初回相談料が無料の弁護士をご紹介
- ✔追加保険料0円で家族も補償に
※年間の保険料35,400円を365日で割った金額
| IT問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |

| IT問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
名誉毀損とは?名誉毀損となる構成要件とポイント
名誉毀損とは、それが真実か虚偽であるかにかかわらず、ある具体的事実を不特定多数の人が認識できる状態で示すことによって、ある人の社会的な評価を低下させることをいいます。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
公然とは「不特定多数の人が認識できる状態のこと」を指し、事実の摘示とは「具体的な事実を示すこと」を意味します。
これらが備わった状況で他人の名誉を棄損してしまう(=社会的な評価を低下させる)と、刑法第230条に規定される名誉毀損罪が成立することになります。
ただし、名誉毀損罪が構成されるケースであっても、それが公益を図る目的でおこなわれ、摘示された事実が真実であると確認できた場合は、違法性阻却事由に該当するため、処罰の対象にはなりません (刑法第230条の2の1項)。
名誉毀損にあたる表現の例
名誉毀損にあたる表現に該当するかどうかは、表現者が事実の摘示をしているかどうかによります。
たとえば、以下のような具体的な事実を示した場合は、名誉毀損に該当する恐れがあるでしょう。
- 「Aは会社の部下と不倫している」
- 「Bは会社の金を横領して家を新築した」
- 「Cは前科者だ」
- 「ラーメン屋Dの厨房でネズミが走り回っていたのを見た」
名誉毀損に時効はある?
刑事上の時効(公訴時効)は3年となっています。
犯罪行為が終了してから3年を経過すると、検察官は犯人を起訴できなくなります。
また、名誉毀損などの親告罪の場合、被害者が告訴できる期間は犯人を知った日から半年以内となっています。
この期間内に告訴状を捜査機関へ提出し、捜査を開始してもらう必要があります。
一方、民事上の損害賠償請求の時効は「損害が発生したときおよび加害者を知ったときから3年」です。
それまでに損害賠償請求の訴訟を提起するなどしましょう。
なお、時効とは別に「除斥期間」というものが定められており、権利を侵害されたときから20年が過ぎると、損害賠償請求権自体がなくなってしまいます。
侮辱やプライバシー侵害との違い
名誉毀損と似ている問題に、侮辱やプライバシーの侵害などがあります。
以下でこれらの違いを確認しましょう。
侮辱罪|事実の摘示がない場合に成立する
侮辱とは、不特定多数の人が認識できる状態で誹謗中傷をしたり、暴言を吐いたりすることで、ある人の社会的な評価を低下させることをいいます。
名誉毀損との違いは事実を摘示しているかどうかという点で、「Eはブス」「Fはバカ」などのように事実の摘示がない場合は侮辱罪に該当します。
侮辱罪の法定刑は2022年7月7日に引き上げられ、現在は「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」となっています。
プライバシー侵害|本人が望まない私生活上の未公開情報を公開されると成立する
プライバシー侵害とは、私生活上の未公開の情報を、本人が望んでいないにもかかわらず、第三者に開示・公開されることをいいます。
名誉毀損との違いは刑法上の刑事罰があるかどうかという点で、プライバシー侵害は刑法に規定されていないため刑事罰がありません。
ただし、プライバシー侵害に伴い名誉毀損が成立する場合もあります。
この場合は名誉毀損にあたるのか
本人は、名誉毀損をしたつもりがなくても、その発言や状況から他人の社会的地位を低下させている場合は名誉毀損に該当する可能性があります。
ここでは、名誉毀損に該当する可能性がある意外なケースについて紹介します。
部下への叱咤激励メールで名誉毀損?
1つ目は、会社の上司が部下へ叱咤激励のメールを送った場合です。
たとえば、「やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います。当センターにとっても会社にとっても損失そのものです。」といった、叱咤激励とも侮辱表現とも捉えられるメールを職場内に一斉送信してしまうと、名誉毀損が成立する可能性があります。
【参考記事】
労働基準判例検索-全情報
配偶者の浮気の証拠をSNSで晒したら名誉毀損?
2つ目は、配偶者や第三者が残した浮気の証拠などをSNS上で公開した場合です。
TwitterやLINEグループのような不特定多数の人が閲覧できるSNSの場合、「公然の場」として認められることが多く、事実を摘示してしまうと名誉毀損になる可能性があります。
ただし、DM(ダイレクトメッセージ)の場合は「公然の場」にはなりません。
飲食店などを口コミサイトで酷評したら名誉毀損?
3つ目は、口コミサイトで飲食店などを酷評した場合です。
口コミサイトは公開の場であるため、投稿内容によっては名誉毀損が成立します。
たとえば「料理にゴキブリが入っていた」などと書き込んだ場合は、事実を摘示し社会的地位を低下させているため、名誉毀損が成立する可能性があります。
なお、「美味しくなかった」などの主観的感想の場合は、刑事上の名誉棄損罪は成立しないですが、民事上の不法行為が成立する可能性はあるでしょう。
ヘイトスピーチのような発言をしたら、侮辱罪?名誉毀損?
4つ目は、ヘイトスピーチをした場合です。
ヘイトスピーチとは、特定の民族や国籍の人々・子孫を日本から追い出したり、彼らに危害を加えたりしようとする言動のことをいいます。
2019年11月29日に京都地方裁判所は「朝鮮学校に対して、ヘイトスピーチをおこない学校法人の名誉を傷つけた」行為者に対し、名誉毀損を認め50万円の罰金刑を言い渡しています。
ヘイトスピーチをしている場合でも名誉毀損になる可能性はあるでしょう。
名誉毀損の刑事上の責任と民事上の責任について
刑事上の責任(懲役や罰金など)と民事上の責任(損害賠償責任)は異なります。
ここでは、名誉毀損による刑事上の責任と民事上の責任をそれぞれ確認しましょう。
名誉毀損罪の刑事罰
刑法第230条1項では 「3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金」と定めており、刑罰としては比較的重い部類に入るといえます。
警察庁の『令和2年の犯罪』によると、2020年の名誉棄損罪の認知件数は805件、検挙率は78.1%となっており、いずれも過去10年間で最も高い数値となっています。
名誉毀損の民事上の責任と慰謝料相場
民事上の責任には、損害賠償金(慰謝料)の支払い、原因となった表現の削除、謝罪広告の掲示などがあります。
裁判によって認定された慰謝料の平均額は180万円、中央値(=相場)は100万円となっていますが、状況によって大きく異なります。
被害者の損害が大きいものや、悪質性が高いものなどは高額になる傾向があります。
名誉毀損で訴えるには?刑事告訴と民事上の損害賠償請求の流れ
名誉毀損は「親告罪」であり、被害者が告訴しない限り公訴提起することができません。。
ここでは、相手方を刑事告訴する場合と民事事件として慰謝料請求する場合の大まかな流れについて確認しましょう。
刑事告訴の流れ
1.名誉毀損について警察に相談し、告訴状を提出する
名誉を棄損した相手を刑事告訴する(=処罰を求める)には、警察に対して告訴状を提出することが第一歩となります。
告訴とは、被害者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことを指します。
告訴状を実際に作るのは警察であり、捜査の必要性が低いと判断された場合は告訴状が作られない可能性があります。
2.警察が捜査し犯人を逮捕、裁判で有罪になれば刑事罰を受ける
告訴状の内容をもとに警察はその犯罪について捜査を開始します。
犯人がわかっている場合は、警察は被疑者として呼び出し、事情聴取などをおこないます。
一方、犯人がわかっていない場合は、まず犯人の捜索活動がおこなわれます。
捜査機関によって逮捕・起訴された犯人は、刑事裁判を受けることになり刑事責任を負うことになります。
民事上の損害賠償請求の流れ
1.発信者情報開示請求などをおこない、加害者を特定する
名誉を毀損した人物が家族や職場の上司・同僚などであれば加害者の特定は難しくないですが、SNSやネット掲示板などで名誉毀損されている場合は加害者を特定する必要があります。
インターネット上で名誉毀損をされている場合は、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求をおこない、加害者を特定することになるでしょう。
2.協議・調停・訴訟のいずれかで請求額を確定する
加害者を特定できたら、民事上の不法行為に基づく損害賠償請求を開始します。
基本的には当事者同士の協議(話し合い)からスタートしますが、協議で話がまとまらない場合には、調停や訴訟に移行し、慰謝料や削除要求、謝罪広告の掲示などを求めることになります。
弁護士に相談しておけばサポートしてくれるので安心できるでしょう。
覚えのない誹謗中傷、ネットストーカーに、鳴り止まないいたずら電話、個人情報の流出…
些細なきっかけから発展してしまったネットでのトラブルの解決に必要な弁護士費用に
もう悩まない「ベンナビの弁護士保険」
ベンナビ弁護士保険は追加0円で離れて住む親や子まで補償
少ない負担で幅広い法的トラブルに備え、多くの補償を受けたい方に
「ベンナビ弁護士保険」のここが「スゴい」
- 初回相談料が無料の弁護士をご紹介可能
- 1日約96円で契約中は通算1000万円までの手厚さ※1
- 自分だけでなく「家族」もしっかり守りたい。追加保険料0円の家族割※2
- 特定偶発事故は1事件330万円。一般事故は1事件110万円を限度額とした手厚い補償
入力30秒で「ベンナビ弁護士保険」がよくわかる資料を一括ダウンロード
「あなた」と「ご家族」まで。まるで「顧問弁護士」がついているような安心感を
※1 年間の保険料354,00円を365日で割った金額
※2 保険契約者の配偶者及び保険契約者の65歳以上の親(血族のみ)と30才未満の未婚の実子が対象
名誉毀損による民事上の慰謝料請求が認められた事例
名誉毀損の被害に遭った場合、加害者に対して民事上の不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
ここでは、名誉毀損による民事上の慰謝料請求が認められた事例について確認しましょう。
事例1:SNS上のなりすましに伴う名誉毀損行為
SNS上で、顔写真を勝手に使用するなどして別の人物になりすまし、そのうえで第三者を罵倒する投稿を継続的に投稿していた加害者の行為が名誉毀損に当たるとする判決がありました。
民事上の損害賠償として、慰謝料60万円と加害者特定などに要した弁護士費用70万円、合計130万円の支払いが認められました(平成29年大阪地裁)。
事例2:在日コリアンの学生を侮辱したことに伴う名誉毀損行為
加害者が自身のブログに被害者を侮辱する内容を投稿したことにより、在日コリアンの学生の名誉が毀損されるという事件がありました。
一審では91万円の支払い命令が出され、控訴審では130万円に増額されています。
加害者の悪質性と被害者が多感な時期であることを考慮し、精神的苦痛が大きいと判断されました(令和3年東京高裁)。
【参考記事】
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
事例3:教授の論文の捏造・論文を指摘したことに伴う名誉毀損行為
「国立大学の教授の論文に捏造・改善がある」として告発する旨の文書をインターネット上に公開したけれど、その主張の裏付けが不十分であったため真実と言えずに教授の名誉を毀損してしまった事件です。
裁判所は被告らの主張が真実とも虚偽とも言えないとし、被告らに110万円の支払い命令を出しました(平成25年仙台地裁)。
【参考記事】
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
名誉毀損事件を弁護士に依頼するメリットと費用相場
加害者(犯人)が特定できていない状況では民事上の損害賠償請求ができません。
また、加害者が特定できている状態でも、法律知識などがなければ損害賠償を請求するのは難しいでしょう。
このような状況を打破するためには、弁護士へ積極的に相談することをおすすめします。
ここでは、弁護士に依頼するメリットと費用の相場を解説します。
名誉毀損で弁護士に依頼するメリット
裁判手続きや交渉など全て任せられる
名誉毀損の被害に遭った場合、民事上の損害賠償請求をするには、加害者の特定や加害者との示談交渉などが必要になります。
また、刑事上の処罰を求めるなら、捜査機関に告訴状を提出しなければなりません。
弁護士に依頼した場合は、裁判手続きや示談交渉などを任せることができ、必要に応じて捜査機関に同行もしてくれるでしょう。
精神的な負担を軽減できる
手続きを全て委任できることに加えて、「加害者をしっかりと特定し、投稿内容などを削除し、受けた被害を回復できる」という道筋が見えてくることで、精神的にも落ち着きを取り戻すことができます。
自身では解決できない心の負担を弁護士へ委任することで軽減することができるのです。
早期解決ができる
警察が捜査を開始して加害者(犯人)が特定されるまでには、どれだけの時間がかかるのか見当もつきません。
弁護士へ委任することで物事がスムーズに動き出し、早期の解決を期待することができます。
名誉毀損事件の弁護士費用相場
弁護士に支払う費用は着手金、報酬金、その他実費の3つに大きく分けられます。
金額はケースによって異なりますので、詳しくは弁護士事務所に確認してください。
「弁護士費用が不安」という方は、弁護士保険を活用する方法もあります。
いざというときに備えておけば、法的トラブルから身を守ることができます。
着手金
着手金とは、弁護士に依頼した時点で支払う事案に着手するための費用ですが、加害者1人あたり(投稿者が複数いる場合はその1人ずつ)10~30万円が相場とされています。
法律事務所によっては着手金のかからないところもあります。
成功報酬金
報酬金とは事件が解決した際に発生する費用で、ひとつの目安としては、認められた慰謝料の16%(ただし300万円まで。それを超える場合は認められた金額の10%+18万円)という計算式を挙げることができます。
その他実費
これとは別に、加害者特定の手続きにかかる費用が発生します。
覚えのない誹謗中傷、ネットストーカーに、鳴り止まないいたずら電話、個人情報の流出…
些細なきっかけから発展してしまったネットでのトラブルの解決に必要な弁護士費用に
もう悩まない「ベンナビの弁護士保険」
ベンナビ弁護士保険は追加0円で離れて住む親や子まで補償
少ない負担で幅広い法的トラブルに備え、多くの補償を受けたい方に
「ベンナビ弁護士保険」のここが「スゴい」
- 初回相談料が無料の弁護士をご紹介可能
- 1日約96円で契約中は通算1000万円までの手厚さ※1
- 自分だけでなく「家族」もしっかり守りたい。追加保険料0円の家族割※2
- 特定偶発事故は1事件330万円。一般事故は1事件110万円を限度額とした手厚い補償
入力30秒で「ベンナビ弁護士保険」がよくわかる資料を一括ダウンロード
「あなた」と「ご家族」まで。まるで「顧問弁護士」がついているような安心感を
※1 年間の保険料354,00円を365日で割った金額
※2 保険契約者の配偶者及び保険契約者の65歳以上の親(血族のみ)と30才未満の未婚の実子が対象
最後に
名誉毀損のトラブルに巻き込まれるリスクは日に日に高まっており、知らない間に名誉毀損の被害者になっている可能性もあります。
加害者の特定や損害賠償請求をするには弁護士の協力が欠かせませんが、弁護士に依頼するには高額な弁護士費用を支払わなければなりません。
そこでおすすめなのが「弁護士費用保険」に加入しておくことです。
一般民事事件がカバーされている弁護士費用保険に加入しておけば、名誉毀損や誹謗中傷などの被害に遭った場合でも弁護士費用を保険で支払うことが可能です。
もちろん、名誉毀損や誹謗中傷以外のトラブルにも幅広く対応することができます。
名誉毀損などのリスクに備えて、弁護士費用保険への加入を検討してみるとよいでしょう。
| IT問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |