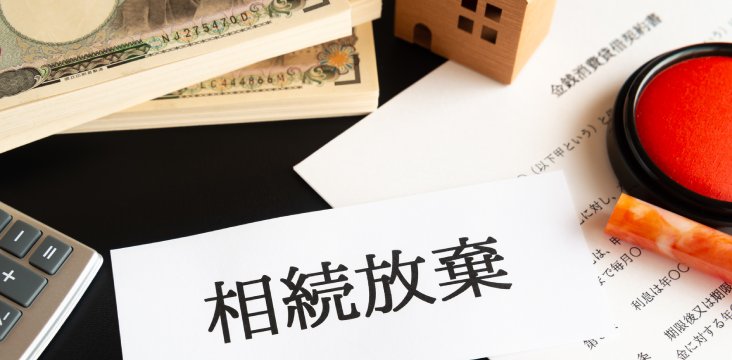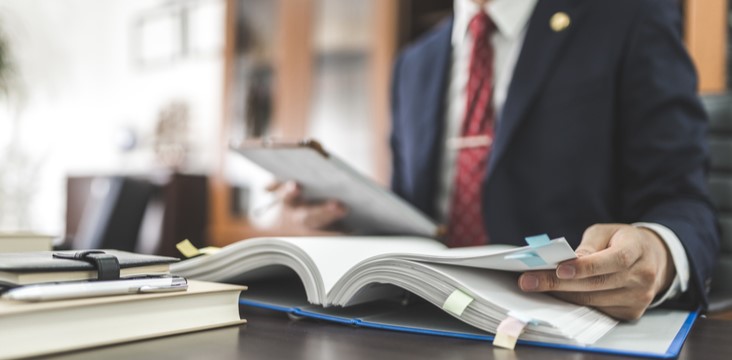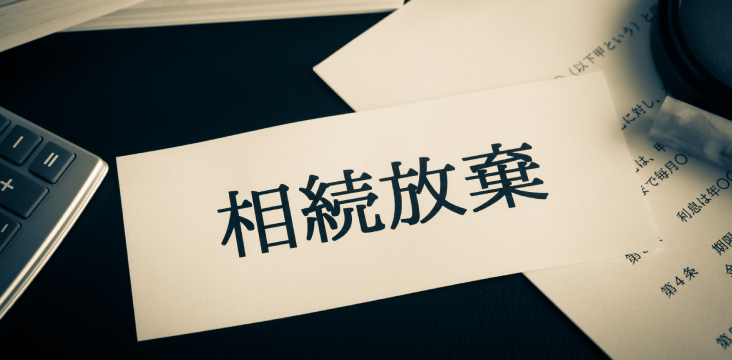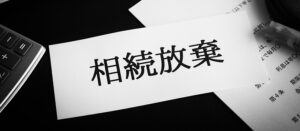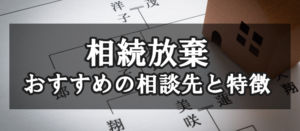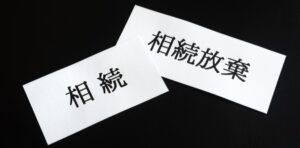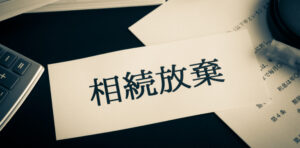これから相続を予定している方や、今後の相続に不安がある方のなかには、事前に相続について誰かに相談したいという方も多いでしょう。
相続相談は、市役所・区役所・弁護士・司法書士・税理士などで受けられますが、それぞれ対応可能な相続手続きが異なるため、相談内容に応じて適切な相談先を選ぶ必要があります。
本記事では、相続の相談はどこにすべきか迷っている方に向けて、主な相続相談の窓口と、相談内容別のおすすめ相談先、相談前に準備しておくべきことなどを解説します。
相続に関する悩みや疑問を抱えている方は、ぜひ参考にあなたにぴったりの相続相談先を見つけてください。
相続の相談先で悩んでいるなら弁護士の無料相談を利用するのがおすすめです。
なぜなら、相続について最も幅広い問題に対応できるのは弁護士だからです。また、万が一相続人同士でトラブルになっても、弁護士に依頼すれば交渉や調停などを全て任せられます。
「ベンナビ相続」では、以下のような弁護士を簡単に見つけることができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
| 相続問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |

相続の相談はどこにするのがいい?6つの相談先の違いを解説
相続に関する相談ができる主な窓口は、以下のとおりです。
- 市役所・区役所
- 銀行
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
相談先ごとにメリットや強みが異なるので、まずはそれぞれの特徴を押さえておきましょう。
|
相続を相談できる主な窓口とそれぞれの強み・メリット |
|
|
相談先 |
強み・メリット |
|
市役所・区役所 |
✔無料で弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談できる ✔自治体によってはパンフレットなどで今後の手続きを教えてくれる |
|
銀行 |
✔専門スタッフが相続に関するアドバイスやサポートをしてくれる ✔各種士業との繋がりがあり、専門家や専門窓口を紹介してくれる ✔相続した資産を運用するためのアドバイスやサポートが得られる |
|
弁護士 |
✔依頼人に代わり、ほかの相続人と交渉をおこなってくれる ✔遺産分割調停や審判、訴訟なども代理でおこなってくれる ✔遺言書の検認手続きの申請や遺言書の案を作成もしてくれる ✔遺留分侵害額請求や遺言無効確認訴訟などにも対応してくれる |
|
司法書士 |
✔相続登記や名義変更などに関するアドバイスがもらえる ✔相続登記や名義変更などの手続きを依頼することができる |
|
税理士 |
✔相続税や所得税など税金に関する相談を受け付けてくれる ✔相続税の申告や故人の準確定申告などの手続きを依頼できる ✔生前であれば、相続税対策のアドバイスをもらうことができる |
|
行政書士 |
✔係争がない場合であれば、遺産分割協議書などの作成を依頼できる ✔行政機関に提出する必要がある資料の作成・代行などを依頼できる |
相続の相談先は相談内容に合わせて選ぶ
相続に関する相談先は、「協議を円滑に進めたいのか」「相続税に関する申請をしたいのか」など相談内容によって異なります。
相続相談をどこにすべきかで迷ったら以下を参考に、自分にあった相談先を選んでみましょう。
|
相続に関する主な相談内容とおすすめの相談先 |
|
|
主な相談内容 |
おすすめの相談先 |
|
相談先や手続きを知りたい |
役所、銀行、葬儀屋 |
|
相続人の調査・確定がしたい |
弁護士、司法書士、税理士 |
|
相続財産の調査がしたい |
弁護士、司法書士、行政書士 |
|
遺言の検認がしたい |
弁護士、司法書士 |
|
相続のトラブルを解決したい |
弁護士、(司法書士) |
|
相続登記に関する相談をしたい |
司法書士、(弁護士) |
|
相続税に関する相談をしたい |
税理士 |
|
書類作成を依頼したい |
行政書士、弁護士、司法書士 |
|
相続後の資産運用を相談したい |
銀行 |
市役所・区役所|何から始めればいいかわからない方
市役所や区役所などの行政機関では、無料で相続相談が可能です。
相続トラブルなどの具体的な対処をお願いすることはできませんが、手続き上の疑問やどうすべきか迷っているなど、相続全般にかかわる相談がしたい方には向いているでしょう。
相談のほかにも、死亡届の提出時に「おくやみパンフレット」を渡してくれるなどのメリットもあります。
また、自治体が主催している相談会では、弁護士や税理士といった専門家が対応してくれるので、具体的なアドバイスをもらえるでしょう。
市役所・区役所での相続相談は、常におこなっている場合もあれば、定期的な相談会を開催している場合もあります。
受付時間や開催状況などの詳しい情報は、各自治体のホームページで確認しましょう。
銀行|相続した資産の運用について相談したい方
銀行も相続の相談に応じてくれる場合があります。
普段から資産継承をテーマとした相続の無料セミナーをおこなっている銀行もあるようです。
ただし、基本的にはコンサルティングサービスであり、所定の手続きを代行してくれるわけではありません。
普段から取引がある弁護士、司法書士、税理士などの専門家を紹介することがメインとなるでしょう。
弁護士|相続のトラブルについて相談したい方
「遺言の内容に納得がいかない」「遺留分を侵害されている」など、相続に関する争いがある場合は弁護士に相談しましょう。
最近では、初回相談が無料の弁護士事務所も増えています。依頼するか決めていなくても、無料相談を利用することで、弁護士に依頼すべきかどうかも含めて判断できるでしょう。
弁護士に相談したい場合は、相続問題が得意な弁護士事務所を頼ったり、法テラスなどの公的機関を利用したりするのがおすすめです。
ベンナビ相続|相続問題が得意な弁護士を探したい方
「ベンナビ相続」は、相続問題の解決を得意としている弁護士事務所が多数掲載されているポータルサイトです。
住んでいる地域と相談したい分野を選択することで、近くの弁護士事務所の中からニーズに合った事務所を探すことができます。
相談できる分野は、相続トラブル、遺産分割、遺留分、相続放棄、代襲相続、相続人調査、相続財産調査など多岐にわたります。
相続問題が得意な弁護士を効率よく探したいなら、ベンナビ相続を利用してみましょう。
| 相続問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
法テラス|弁護士費用を抑えて弁護士に依頼したい方
法務省が所管している法テラス(日本司法支援センター)では、「情報提供業務」といって法的トラブルを解決するのに役立つ窓口やサービスなどを紹介するサービスを提供しています。
また、「民事法律扶助業務」といって経済的な理由で弁護士費用を用意できない人に向けて、弁護士や司法書士による無料相談や、弁護士費用・司法書士費用の立て替え制度なども提供しています。
無料相談や立て替え制度などを利用したい方は、まずは「最寄りの法テラス」に問い合わせをしてみましょう。
司法書士|不動産や預貯金、有価証券などを相続する方
相続財産に不動産や預貯金、有価証券が含まれる場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
土地や建物といった不動産を相続する際は、管轄の法務局で相続登記の手続きをおこなう必要があります。
また、預貯金や株などの有価証券が含まれている場合は、名義変更の手続きが必要になります。
不動産や預貯金、有価証券を相続し、相続登記や名義変更が必要な場合には司法書士に相談しましょう。
税理士|相続税や準確定申告の相談がしたい方
相続で税理士に相談するケースは、主に相続税を申告する場合や準確定申告をする場合などです。
税金の申告書の作成は複雑なので、自力でおこなおうとすると負担が大きくなります。
また、準確定申告という亡くなった人の所得を確定するための手続きも必要になる場合があります。
税金に関する相談や申告書の作成などを依頼したい場合には、税理士に相談しましょう。
相続税の相談が必要になるのはどんなとき?
相続が発生したからといって、必ずしも相続税の申告が必要になるわけではありません。
相続税の課税価格が基礎控除額を下回るケースでは、課税されないため申告する必要がないのです。
基礎控除額は、3,000万円と法定相続人の人数×600万円で計算できます。
たとえば、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は4,800万円(3,000万+(600万円×3人))となるため、課税価格が4,800万円以下であれば申告する必要がないのです。
相続税の申告が必要かどうかも含め、心配であれば税理士に相談するとよいでしょう。
行政書士|書類作成だけを手伝ってほしい方
行政書士は、行政機関へ提出する書類の作成・代行をしてくれます。
たとえば、係争がない場合の遺産分割協議書の作成を依頼することができます。
また、自動車やバイクの名義変更の手続きや、森林を相続した場合の届出書の提出などを依頼することも可能です。
書類作成や名義変更だけを依頼したいのであれば、行政書士に相談するのもよいでしょう。
相続の相談前に事前に準備しておくべきもの
どこに相談するかによって準備するものはやや異なりますが、最初の相談で最低限以下のものは用意しておきましょう。
- 家族構成
- 相続人の名前と住所
- 相続財産
まず家族構成をまとめておきましょう。
被相続人が再婚している場合、前の配偶者との間の子どもも相続人となります。
名前と住所をまとめておくことで相続発生後の連絡がスムーズになります。
また、できる限り財産を洗い出しておきましょう。
現預金や不動産など、事前に資産の種類や金額を整理できていれば、相続発生後の手続きの負担が少なくなります。
相続相談にかかる費用の相場・目安
相続について弁護士、司法書士、税理士などに相談する場合、一般的には相談料が必要になります。
相談先ごとの相談料の相場・目安は、以下のとおりです。
|
相続の相談にかかる費用の相場 |
|
|
相談先 |
相談料の目安 |
|
弁護士 |
1時間あたり5,000~1万円程度 |
|
司法書士 |
1時間あたり5,000~1万円程度 |
|
税理士 |
1時間あたり1万円程度 |
なお、相談先によって相談料は異なるため、予約時や相談時にいくらかかるのかを確認しておきましょう。
初回無料相談OKの専門家も多いので「相談するだけでお金がかかるのは…」と不安な方は、ぜひ以下より無料相談ができる弁護士を探してみてください。
まとめ|相続の悩みに合わせて相談先を選ぼう
相続のことを相談できる専門家には、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などがいますが、それぞれ専門分野や対応可能な手続きが異なります。
たとえば、相続人同士で争いになっている場合や、裁判手続きが必要になっている場合は、弁護士以外では対応するのが難しいです。
もし弁護士に相談する必要があるなら「ベンナビ相続」を使い、近くの相続問題が得意な弁護士事務所を探し、相談することをおすすめします。
| 相続問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |